当サイトはアフィリエイトプログラムを利用して商品の紹介を行っています。
【法務省は部落差別をしている?】
【土地家屋調査士試験】の受験生が作った
個人的な資格難易度表
【部落民は暴力団に入るしかない社会を法務省が作った】
個人的な資格難易度表
| 殿堂入り | 漢字検定3級 日商簿記検定2・3級 |
|---|---|
| A | なんとか士 |
| B | 土地家屋調査士 |
| ↑何か不正があるのではないかと勘違いしてしまうくらいに難しい。 たぶん合否が試験の出来ではなく、何か別のもので決まっていると思います。 |
|
| C | 行政書士 社会保険労務士 |
| D | 宅建 |
| ↓勉強すればたぶん誰でも受かる。 | |
| E | ビジ法2級 運転免許 3級FP技能士 乙種4類 測量士補 法検3級 法検4級 |
| F |
すべてがFになる?
|
A、B、C間はワンランク上がるたびに難易度がグンと上がります。仮に3倍難しい資格試験があるとしても1,000円が3,000円になると考えると大した差はありませんが(そういう意味では法検3級も法検4級もどちらも同じようなものですが)、同じ3倍でも100万円が300万円になって、さらにそれが900万円になったりしたら差額が大変なことになります。A、B、C間にはそういう衝撃的な差があります(私にとってはそう。お金をたくさん持っている人なら「100万円でも300万円でも同じだよ」と言うかもしれません)。
各資格試験の感想
日商簿記検定2・3級
私はどの月が何日まであるかを日商簿記3級で覚えました。テキストに「西向く士」(にしむくさむらい、246911)と書いてあったからです(11は漢字です。十一を縦(↓)書きにして士(=さむらいと読む)にしています)。しかし、試験には落ちました。2・3級併願で受けたのですが、どちらも落ちました。点数の通知を受けられるようにはしていなくて(というのも両方とも受験1回目で合格する気でいたため、点数なんかどうでも良いと思っていた。点数を知るためには受験料とともに別途、成績通知費の払い込みが必要です)、何点だったのかは分かりません。
私には文字や数字を入れ替えるクセがあり、それがまずかったのかもしれません。たとえば六法で「345条」を引くときは、いつのまにか「453条」を探しているし、パソコンで「床面積」と打とうとすると「床戦めき」になります。野菜の種の説明書に「たねまき後は~」と書いてあるのを見て「これトマトの種なのに、タマネギ後って何だろう?」と疑問に思うことがあります。ちなみに漢字検定3級も中学生のときに受験して落ちました。もう2度と受けないため殿堂入りです。
危険物取扱者乙種4類
乙種4類は近所の職業高校生と一緒に受験しました。テキストは試験前に近所の工業高校生から借りました。通称「赤本」という市販はされていない本です(株式会社 向学院が通販しています)。赤本はテキストと問題集が一体になっているタイプの本で、小学生が使う算数の教科書や、職業高校生が使う数学の教科書なみに薄い本です。短期合格が目指せます。▲勉強期間は4日でした。1日3時間×4日(内訳は物理・化学1日、性質・消化1日、法令2日)の計12時間で取れました。「こんなの3日あれば受かるよね?」と知り合いに言ったところ、じゃあ3日で受けてみろと言われたので受けました。試験前になって3日で合格できるかどうかが心配になってきたので、勉強は試験4日前から始めました。
この試験を受けると「身分証明で危険物取扱者免状を出すと危険人物だと思われるから出せない」(高校生だからまだ運転免許は持っていない)、「あのガソリンスタンド、法定距離取ってないよね?」などの会話ができるようになります。
3級FP技能士
3級FP技能士は、なんとか士の勉強中に課税標準という言葉が出てきたときに役に立ったと思った。課税標準は土地家屋調査士試験でも登録免許税のところに出てきますよね。ほかにも新聞に出てくる日銀短観とか、なんとかかんとか指数(景気動向指数?)とかの言葉の意味も分かるようになりました。▲課税標準、日銀短観、なんとかかんとか指数など聞きなれない言葉が多く、日商簿記検定や危険物取扱者乙種4類と比べると、取っつきにくくて難しかったようなイメージがあります。勉強時間は毎日2時間を44日(休日抜きの2か月間)くらいです。
私がこの資格試験を受けた最大の理由は、この資格試験がジュニアマイスター顕彰制度でB12点の工業系の技能士と同じく、資格の名称に「技能士」という言葉が使われていたからです(次点は国家資格だったから。それに難易度が低そうだったから)。もし私が職業高校生との関わりを持っていなかったら、たぶん私はこれまでに紹介した「日商簿記検定2・3級」「危険物取扱者乙種4類」「3級FP技能士試験」の3つは受験しなかったと思います。
宅地建物取引主任者(現・宅地建物取引士)
受験動機
宅建は父が1970年代~1990年代に独学や通信教育で勉強しており、よくネットでも「法律系資格試験の登竜門」と言われているので受けた。父は中学生のときに10段階の相対評価で2や3(100人中85~98位)の成績を取っており、偏差値30台の高校に進み、そこでも成績は6が1個あるくらいであとは全部4くらいでしたが、大学進学率25%強(男子40%、女子12%)の時代に偏差値30台の工学部を出て不動産販売会社に就職しましたが、宅建試験には合格していません。父も母も母校の高校や大学、短大が廃校になったり倒産したりしています。高校生の子供から無利子で借金し、警備員の祖父から食べ物を分け与えてもらって生きてきました。
| 成績 | 割合 | 高校偏差値の目安 | 大学進学率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25%時代 | 2013年 | |||||
| 10 | 2%(1~2位) | 70以上 | 男 子 40 % |
女 子 12 % |
全 体 49.9% 男 子 54.0% 女 子 45.6% |
|
| 9 | 5%(3~7位) | 65以上 | ||||
| 8 | 9%(8~16位) | 5% | 60以上 | |||
| 4% | ||||||
| 7 | 15%(17~31位) | 55以上 | ||||
| 6 | 19%(32~50位) | 9% | 50~ | |||
| 10% | ||||||
|
普通の人(高校偏差値50)
|
||||||
| 5 | 19%(51~69位) | 50~ | ||||
| 4 | 15%(70~84位) | 45未満 | ||||
| 3 | 9%(85~93位)境界知能(※) | 40未満 | 父(なぜか四大卒) | |||
| 2 | 5%(94~98位)境界知能(※) | 35未満 | ||||
| 1 | 2%(99~100位)知的障害(※) | 30未満 | ||||
当時大学に進学していた25%というのが18歳人口の上位25%とイコールではないことは明らかです。割合から言って男子は中学校で成績6相当でも大学に進学しているのですから(性別による能力差はないことを前提として。つまり成績1~10に満べんなく男女が入っていると仮定して)。これは全国の中学生が同じ1つの学校にいたときの話です。中学受験でいなくなる方もいるので普通の公立中学校だともう少し成績が良くないと駄目だったかもしれません。また、大学進学率には男女格差だけはでなく、地域格差もあったかもしれません。
また、現在の物価に換算した上での1967年における大学年間授業料は、私立理工系で36万9,435円と聞きますが(私立理工系の年間学費は現在150万円前後)、経済的な負担は昔のほうがずっと軽かったのですね。たとえ中学校で成績2や3でも年間36万円(これは私立理工系の話で、国立や文系ならもっと安い)で済むなら大学に行かせておこうという親も増えると思います。仮に学生が借金をして大学に進むにしても負担はずっと軽くなります。
↓弟から見た両親の様子↓
私の上の弟も小・中学生のときの成績が良いほうではなく、たとえば算数・数学は一番低いものだと小学生のときに0点、中学生のときは5~10点くらいだったと思いますが、そんな弟でも大学の理工系学部では成績優秀のため学費が免除になるくらいなので、もしかすると昔よりも大学進学率が大幅に増えている女子の参入が少ない理工系の学科は狙い目なのかもしれません。国立大学の募集人員も文系学部よりも理系学部のほうが何倍も多くて、国立でも特に理工系の学部なら成績が少々良くなくても入りやすいのですよね。たとえば鳥取大の2020年の前期日程の募集人員は大学全体で709名ですが、そのうち文系学部の募集人員は地域学部の104名のみです。徳島大は同条件で募集723名中、文系学部は総合科学部の85名のみです。各大学の募集人員はこちらで確認できます。
もし部落差別がなければ違う人生を送っていたかもしれません。父も母も中卒や高卒で就職できていれば高校や大学には行かなかったかもしれませんし、差別がなければ大学新卒で非正規雇用に就くこともなかったかもしれません。結婚相手も違っていたかもしれません。弟(伯爵レグホン軍曹)も2007年9月以前にはすでに差別を実感していたようですね(上から4つ目の絵を参照のこと)。
勉強期間
私は受験1年目は8月から現「どこでも宅建士 とらの巻」で勉強しました。「夏からはじめて合格!」とこの本の表紙に書かれていたためです。ちなみに受験1年目は過去問は買いませんでした。当時は資格試験の勉強にそんなものが必要だとは思っていなかったためです。▲受験2年目はパーフェクトシリーズのテキストと過去問(年度別10年分)を使って、結局、学生時代の夏休みを中心に約3か月×2回の勉強で試験に合格しています。
勉強方法
私はいつもテキストばかり読んでいて、過去問は実力試しの模試のつもりで解いていて、今思うとこれはあまり良い勉強方法ではなかったです。テキストを読むよりも過去問を解くほうが手っ取り早く実力が付きます。▲過去問も「パーフェクトシリーズの分野別の過去問題集(5年分収録)」と、同じく「パーフェクトシリーズの年度別の過去問題集(10年分収録)」が同じ値段だったため、どうせなら収録年数が多いほうが良いと思って年度別10年分のほうを買っており、当時は年度別と分野別の違いを意識することもなかったです。独学者が過去問で勉強するなら分野別のほうが向いていると思います。同じ分野の似たような問題を何度も解くうちに次第に理解も深まっていくと思います。
社会保険労務士
受験動機
私が社労士試験の勉強を始めた理由は、学生時代に法学検定2級を受けた結果、受験前に基本書を読んだだけの労働法が8/10点も取れていて、労働法ちょろいなと思ったからです。社労士試験はとても簡単な試験です。労働法という分野それ自体が憲法、民法、刑法等と比べると簡単なのだと思います。暗記が中心で頭を使うようなところがありません。社労士試験の一般常識の問題は、大学で社会保障関係の講義を受けていると比較的受け入れやすいと思います。
勉強期間
私は受験1年目は4月からTACの「ハイレベルテキスト」(現「よくわかる社労士 合格テキスト」。というのも1冊本は行政書士試験で懲りていたため)を読み、過去問はTACの「スピードマスター」(1冊本。7年分の過去問。今はもう売られていない本)を使用。8月の試験日までに①労働法・労働保険法関係のテキスト5冊&過去問、②社会保険法関係のテキスト3冊&過去問を、ひと月ごとに交代交代に進め、最後のひと月は一般常識のテキスト2冊と、すべての範囲の過去問を解くことに使った。
受験2年目は「月刊 社労士受験」を暗記カードと問題演習目的で買い、過去問を「力の3000題」(10年分の択一式過去問。この本には選択式の過去問は載っていませんでした)に買い換え、「別冊ハイレベルテキスト直前対策&一般常識・統計╱白書╱労務管理」「完全無欠の直前対策」「最強の一般常識問題集」「誌上最強の模試」その他市販の模試を3冊解いて約1年4か月で選択式1科目救済合格しました。
当時は一般常識のテキストに若年男性よりも若年女性のほうが可処分所得が高いと書かれていたと思います。男性と女性を比べると男性のほうが可処分所得が低いというのは、常識知らずな方でも若年~弱者男性向けサイト(相場の50分の1~100分の1程度の収益しかない)を作っている方なら今はもう大体みな実感しているのではないかと思います。
| 若年男性 | 若年女性 | |
|---|---|---|
| 可処分所得 | 低い | 高い |
| 結婚相手の年収 | 低い | 高い |
| 結婚後の 世帯年収 | 低い | 高い |
話をもとに戻しますが、当時はダイレックス(検索しても出てこないので社名を間違えているかも?)という会社の市販模試が本試験の問題よりもはるかに難しくてぜんぜん点が取れなくて試験前に狼狽した覚えがあります。この会社は当時は社労士試験の問題集も出していたと思いますが、その問題集に載っている問題もすごく難しいものばかりだったと思います。難しすぎて試験対策になっていなかったと思います。
難易度
社労士試験はネット上ではなぜか過大評価されていますが、どちらかと言えば宅建試験寄りの難易度です(内容的にも分量的にも)。宅建試験、社労士試験はどちらもマーク式の勉強をしていれば済み、合格基準点が6~7割と低く、試験時間も長くて、問題文を全部読めますし、解答後には見直しまでできます。テキストのページ数も宅建試験が800弱、社労士試験は1冊本が約1,000ですから大して変わりません(私は分冊本で勉強しましたが、他のサイトでよく勧められているのは1冊本ですよね)。
社労士試験は択一式の各肢の問題文は長いですが、頭を使わなくても読めるような内容になっているので、長い文章の問題でも割かしぱっぱと解けます。民法の問題文のように、AがBに何かして第三者のCに何がどうこうというような、順を追って起こったことを理解して、その問題文に何かを当てはめて解くような内容の問題ではなかったと思います。土地家屋調査士試験の不動産登記法総論の地目や建物の種類の問題、測量士補試験の文章問題と同じように、すっと頭に入ってくる問題文を読めばすぐにパッと答えが出ます。
法律関係の資格試験の勉強をしたことがない方が持っていそうな法律関係の資格試験の勉強に対するイメージ(=暗記に次ぐ暗記)に合致していそうなのが社労士試験だと思います。
もし私がこのページの一番上に書いた個人的な資格難易度表のB、C、Dのところを3段階評価から2段階評価に変えるなら「B 土地家屋調査士」と「C 行政書士 社会保険労務士 宅建」に分けていたと思います。社労士試験は宅建試験よりも少し量が多いだけです。宅建試験に受かるなら社労士試験にもたぶん受かると思います。
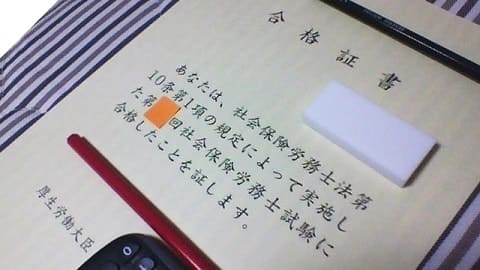
2010年代前半の社労士合格証書。
社労士試験と土地家屋調査士試験の難易度の比較
土地家屋調査士試験と比べると、土地家屋調査士試験の午後の部の択一式の不動産登記法の簡単な問題のみ=社労士試験の全部(択一式・選択式)くらいの感覚です。土地家屋調査士試験の午後の部の択一式は①民法、②不動産登記法、③土地家屋調査士法の3科目ですが、科目ごとに勉強方法がそれぞれ違うため、ただテキストを読んで過去問を解いていれば良いという点で、土地家屋調査士試験の午後の部の択一式の不動産登記法の簡単な問題と宅建試験、社労士試験とで勉強方法がかぶるため、私の中ではそういうイメージが付いています。
土地家屋調査士試験は、午後の部の択一式のほかにも、午前の部(測量士補試験で免除を受けるならそれ)及び午後の部の記述式(計算、論述、申請書、作図)並びに口述試験があります。宅建試験と社労士試験の差よりも土地家屋調査士試験と社労士試験の差のほうがずっと大きいと思います。
勉強に必要な書籍の数も土地家屋調査士試験のほうが比べ物にならないほど多いです。宅建試験、社労士試験はテキスト、過去問、模試の3つくらいで済みますが、土地家屋調査士試験は午後の部の試験対策だけでも20冊強~40冊弱の本が必要です。
社労士試験と土地家屋調査士試験の【試験科目の条文の数】の比較
社労士試験は試験範囲が広いとよく言われていますが、それは本当でしょうか。 次に社労士試験と土地家屋調査士試験の試験科目の条文の数を比べてみましょう。
社労士試験(全907条+α)
- 労働基準法(121条)
- 労働安全衛生法(123条)
- 労働者災害補償保険法(54条)
- 雇用保険法(86条)
- 労働保険料徴収法(48条)
- 健康保険法(222条)
- 厚生年金保険法(105条)
- 国民年金法(148条)
- その他(最低賃金法、労働組合法、労働契約法、介護保険法、国民健康保険法、社会保険労務士法等その他条文でないものも含めてたくさん)
土地家屋調査士試験(全1,754条+α)
- 不動産登記法(164条)
- 不動産登記令(27条)
- 不動産登記規則(246条)
- 不動産登記事務取扱手続準則(146条)
- 土地家屋調査士法(78条)
- 土地家屋調査士法施行規則(49条)
- 民法(1044条)
- その他(不動産登記令別表、建物の区分所有等に関する法律、登録免許税法など)
私には社労士試験の試験範囲が取り立てて広いものだとは到底思えません。社労士試験でも土地家屋調査士試験でも、どんなに試験範囲が広くても(たとえ社労士試験は+αの部分がけっこう多く、また土地家屋調査士試験は不動産登記法のうち権利登記の部分や民法の債権、親族の部分はあまり勉強しないし、+αの部分はごく一部の条文しか見ないという事実があるにしても)、独学だとみんなテキストと過去問(と土地家屋調査士試験は六法と記述式の問題集も)くらいしか勉強に使わないと思います。そしてそのテキストの分量には択一式のものだけでも社労士試験と土地家屋調査士試験との間に約2.5倍の差があるのですよね。
土地家屋調査士試験は最大手の東京法経学院が出している択一式のテキスト(「合格ノート」のこと。私が見ているのはⅠ上、Ⅰ下、Ⅱの計3冊構成だった旧シリーズのものです)だけでも社労士試験の1冊本の約2.5倍の分量があります。これはページ数だけではなく、本の大きさ(B5判とA5判の約1.5倍の違い)も考慮した数字です。
土地家屋調査士試験の勉強は条文だけではない
土地家屋調査士試験の筆記試験の内容は、正確にいうと試験科目として民法、不動産登記法、土地家屋調査士法の3科目が規定されているわけではなく、正式にはたとえば令和3年(2021年)度試験の時点では、
- 民法に関する知識
- 登記の申請手続(登記申請書の作成に関するものを含む。)及び審査請求の手続に関する知識
- 筆界(不動産登記法(平成16年法律第123号)第123条第1号に規定する筆界をいう。)に関する知識
- 土地及び家屋の調査及び測量に関する知識及び技能であって、次に掲げる事項
- 土地家屋調査士法第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うのに必要な測量
- 作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。)
- その他土地家屋調査士法第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
とされており、条文以外の部分もかなり多いです。たとえばどんなに不動産登記法の勉強をしても登記申請書は作成できません。不動産登記法には「AのときはBする」「CのときはDできない」「〇か月以内に〇〇しなければならない」等のことを個別に書いてあるだけで、具体的に登記申請書とはどのようなものなのか、登記申請書の例として登記申請書を1枚の絵として具体的に思い浮かべることができるかというと(一行目に「登記申請書」、二行目に「登記の目的 土地表題登記」などと書かれているあの1枚の紙を思い浮かべることができるかというと)不動産登記法を何度読んでも、たぶんそれは無理だと思います。登記申請書を作成するためには、実際に登記申請書を書いてみるという勉強をしなければなりません。
条文の数だけを比べると社労士試験<土地家屋調査士試験で、具体的にその差が表れている択一式のテキストを見比べるとその分量に約2.5倍の差がありますが、さらに土地家屋調査士試験は登記申請書の作成や作図、計算など条文以外の部分についても学ぶところが多く(ただし、図面の枠だけなら不動産登記規則別記第1号や第2号に載っています。不動産登記事務取扱手続準則52条や53条には建物図面や各階平面図の例示があります)、このような事情が「宅建試験、社労士試験はテキスト、過去問、模試の3つくらいで済みますが、土地家屋調査士試験は午後の部の試験対策だけでも20冊強~40冊弱の本が必要です」というところに、つながっていくことになると思います。
測量士補
測量士補試験は試験前にゴールデンウイークがあるため、休める人はそのときに死に物狂いで勉強できるので短期合格しやすいと思います。
| 測量士補 | 土地家屋調査士 |
|---|---|
| 四則演算と比の計算がメイン。高校1年生程度(数学Ⅰ)の三角関数を使う問題が1、2問出る。 | 数学Ⅰの三角関数、数学Ⅱの直線の方程式、内分点の計算、数学Ⅲの複素数平面を使う。 |
| 問題用紙に三角関数の真数表が掲載されており、三角関数の真数表を丸暗記する必要がない。 | 問題用紙に三角関数の真数表が掲載されておらず、普通の電卓やそろばんで試験問題を解くなら合計98万2,800個(273×60×60個)の三角関数真数表の数字の丸暗記が必要。 |
| 過去問と同じ問題が出る。 | 今のところ平成25年(2013年)度~平成30年(2018年)度は毎年1問目は同じ問題が出ています。2問目以降の計算問題も短い目で見れば簡単になってきています。それでも平成10年代の初め頃以前と比べると今のほうが難しいと思います。 |
| 解答に必要な情報が1か所にまとまっている。 | 問題用紙の枚数が多く、解答に必要な情報が複数のページに分かれており、ページを行ったり来たりする。これは計算ではなく申請書の話ですが、土地・建物の各問につき問題用紙が10ページ弱あり、申請書に何を書かなければならないかは分かっていても、その書かなければならないことが問題文の中のどこに書いてあるかが分からない。 |
| 試験時間に余裕がある。 | 制限時間内にすべての問題を解ききることが困難。解き方を考える時間がないし、普通の電卓やそろばんでは三角関数の真数が分からないため、そもそも解けないようになっている(※)。一部の特殊な電卓(関数電卓)を試験に持ち込んで一部の特殊な操作方法(「1+1=」とかではなく、「SHIFT、tan-1」など)を取らないと答えが出ない。 |
| 電卓を持ち込めない。 | そろばんまたは電卓を持ち込める。 |
| 合格点が低いため、文章問題で点を稼げるなら計算問題は大量に間違えても構わない。28問中18問(約65%)の正解で合格なので、文章問題で15/18点取れれば計算問題は3/10点でも合格できる。とはいえ文章問題よりも計算問題のほうが簡単なので計算問題で点を稼ぐのがおすすめです。 | 例年2、3問出題。計算ができないと正攻法では作図ができなくなり、図面に書く辺長も求められず、また地積が求められないため登記申請書を完成させることもできない。要は計算ができないとほかの部分にも影響が及ぶ。 |
測量士補試験は文章問題なら過去問と一字一句同じ、計算問題も過去問の数字を変えただけというレベルで同じ問題が出ます。難易度は相当低いです。
※ 平成30年(2018年)度以降は土地家屋調査士試験の問題用紙に三角関数真数表が掲載されなくなりました。そのため、もし普通の電卓やそろばんで試験問題を解くなら三角関数真数表の丸暗記が必須になりました。普通の電卓やそろばんで試験を受けようと思っている受験生は、何よりも先にまずは三角関数真数表の丸暗記をしてください。択一式や書式の勉強をした後で三角関数真数表の丸暗記ができないことが分かるとせっかくの苦労が水の泡です。
話がそれますが、法律関係の難しい資格試験のテキストは、その内容を理解できるかどうかは別として、誰でもそこに書いてあることを日本語として読むことはできるため、実際には計算問題と同じように読んでいる本人は何も分かっていないことに気がつきにくい分、計算問題よりもやっかいだと思います。
測量士補試験の計算問題はネット上では「テキストが何を言っているかがよく分からない」「とっつきにくい」等とよく言われています。本当は何も分かっていないのになんとなく分かった気になれる法律関係の資格試験のテキストと違って、計算問題は数字が合わなければ×ですから独学でも自分の理解の浅さに気がつきやすいのだと思います。法律関係の難しい資格試験は独学には向いていないと思います。高級品で実績も抜群の東京法経学院の講座を利用して短期合格するのがおすすめです。
たとえば土地家屋調査士試験の受験案内書を何度読んでも「受験申請書を法務局に持参する場合はその法務局の中で受験票に受験番号のハンコを押されて、そのまま受験票が直接受験生に返却される」ことは分からないはずです。そんなことはどこにも書かれていませんからね。でもそのことを知らないと受験案内書はとても読みにくくて分かりにくいです。特に東京の中央組織に願書を提出させる行政書士試験や社会保険労務士試験とは勝手が違うため、地方でそれらの資格試験を受けたことがある方にとっては、法務局に願書を持参する際に受験票の裏面に切手を貼ったり住所を書いたりするかどうかは困惑しやすいところだと思います(何も知らないと東京までの送料は誰が負担するのだろう? と疑問に思う)。
ジュニアマイスター顕彰制度
ジュニアマイスター顕彰制度では測量士補はA20点です。ちなみに工業系の技能士(FPはだめ)は3級がB12点、危険物取扱者は乙種4類がD4点です。3級FP技能士試験や測量士補試験と比べるとずっと難しい宅建もB12点です。もし現役の工業高校生なら30点以上でジュニアマイスターシルバー、45点以上でジュニアマイスターゴールドになります。
| 測量士補 | A20点 |
|---|---|
| 宅建 | B12点 |
| 乙種4類 | D4点 |
| 合計 | 36点(ジュニアマイスターシルバー) |
ちなみに商業高校には「三種目以上1級合格者表彰制度」があります。全8種の「全商〇〇検定」で1級を3個以上取ると表彰されます。ちなみに工業高校生も「全工〇〇検定」(特に計算技術検定3級)をよく受けています。商業高校生というと簿記検定2級に合格しているイメージがありますが、商業高校生が合格している簿記2級は日商簿記2級ではなく全商簿記2級です。
工業高校生なら国家資格といえば危険物取扱者乙種1~6類(ちなみにこの乙種1~6類のすべての類の試験に合格することを「全類制覇」と言います)や工業系の三級技能士、二級ボイラー技士、第二種電気工事士、工事担当者DD第三種、2級建築施工管理技術検定、2級土木施工管理技術検定などの手軽なものがあるのに(技能士は放課後残って練習しているそうなので手軽とは言えないかもしれませんが……)商業高校生は民間資格ばかり受けていて、国家資格というとITパスポートや3級FP技能士試験くらいしか難易度的に現実的なものがなくて、私には工業高校生は国家資格を取っていて商業高校生は民間資格を取っているというイメージがあります。
また、職業高校生は高校生なのに留年して退学する方が結構いる(入学時の生徒の0~2割弱は卒業時にはいない)イメージがあります。個人的には留年は楽しいものだと思います。高校生でいられる時間が1年増えますし、かかる学費は特に公立ならたかが知れています(大学の高額な学費と比べてみると特にそう思う。大学生の1年間よりも高校生の1年間のほうがはるかに安く済む)。むしろ1年くらい留年したほうが良いと思います。私の近所の職業高校では留年が決まった方は退学してクラーク記念国際高等学校に入る方が多かったようですが、もし私なら何年留年しても退学せずに慣れ親しんだ同じ学校に通い続けていたと思います。
ビジネス実務法務検定2・3級
詳しいことは覚えていないが、3級は何もしなくても過去問が解けたので、いきなり2級の公式テキストから読み始めて、97点とか98点とかの満点に近いような点数を取って合格した覚えがある。2問しか間違えていなかった。3級のことは何も覚えていない。もしかすると受けていないかもしれない。3級の過去問は大学の図書館にあったと思う(テキストの巻末に3年分くらいの過去問が収録されていたと思う)。2級は問題集のようなものは解いておらずテキストを読むだけの勉強だった。
ビジ法2級は公式テキストを読むだけで満点近く取れたため、その頃の私がテキストと過去問で勉強していても合格点をぎりぎり超えるくらいの点数(詳しいことは覚えていないが、合格点+1、2点くらいだったと思う)しか取れなかった宅建試験よりも易しいと思う。ビジ法2級はテキストのページ数も宅建試験のそれの半分くらいしかありません。
法学検定2・3・4級
これも詳しくは覚えていない。というのも、これもビジ法も東日本大震災のときにテキストや問題集が金魚の水槽の水をかぶってしまい、もういらないやと思って合格証書、成績通知書等ともども合格から日が浅いうちに全部捨ててしまったため詳しいことが分からない。法検3級は法学部3年次修了程度とされているが、公式問題集を解けば1年生でも合格できる。というかたぶん1か月くらい勉強すれば法学部とか関係なしに誰でも受かると思います。
法検3・4級はどちらも公式問題集を解けば受かるという意味では難易度はほぼ同じです。測量士補試験も過去問10年分を解けばほぼ確実に受かります。受かりやすさで言えば運転免許の学科試験や危険物取扱者乙種4類よりも法学検定3・4級や測量士補試験のほうが上だと思います。私は運転免許の学科試験は1度落ちていますが、法学検定3・4級や測量士補試験はちゃんと勉強をしていたら落ちるほうが難しいと思います。
なお、法学検定は2012年度から制度がリニューアルされ、2~4級はそれぞれアドバンスト〈上級〉コース、スタンダード〈中級〉コース、ベーシック〈基礎〉コースに名称が変更されました。1級は元から実施されておらず、法検は元々2級が最高級です。▲2級は法学部卒業程度の試験とされています。法検3・4級と違って、過去問を解くだけでは合格は難しいです。私は一度2級を受けて不合格になって以降、もう法学検定は受けていません。受験料が高かったためです。当時2級は受験料が1万2,600円もしました。今(2018年現在)は2級の受験料は9,450円に値下げされています。それでもまだ高いと思いますが。
行政書士
昭和~平成一桁の頃までの行政書士試験の試験問題は今の(と言っても制度が変わっていますが)法学検定4級(法学部2年次修了程度の難易度とされていますが、実際には1週間~1か月くらい勉強すれば法学部とか関係なしに誰でも受かる)と同じくらいの難易度だったと思います。当時の宅建試験の民法の問題と比べてみても、どちらのほうが難しいのか、もしかすると行政書士試験の民法のほうが簡単なのではないかと思うような難易度だったと思います。要は昔は宅建試験もすごく簡単だったと思います。
それが今や法律関係の資格試験はどれも大体、試験問題がすごく難しくなり、行政書士試験も簡単には受からない資格試験になってしまいました。法科大学院を出て行政書士をしている方もたくさんいます(「法務博士 行政書士」と検索するとたくさん出てきます。法科大学院を出た方は法学修士ではなく法務博士になります)。▲土地家屋調査士試験の午後の部の民法と比べてみても、行政書士試験の民法のほうが出題範囲が広くて、内容も難しいと思うくらいです。
法科大学院を出たのに司法試験に受からなかった方の救済措置として行政書士の資格を付与せよと言う方もいます。法科大学院を出るほど法律の勉強をしているなら試験を受けて行政書士の資格を取れば良いのにどうしてそんな救済措置が取りざたされているのかと言えば、試験が難しくなりすぎて法科大学院を出るほど法律の勉強をしていても行政書士試験にすら受からない方もいるためでしょう。司法試験よりも簡単な法律関係の資格試験があることそれ自体が救済措置で、そこに引っかからなければもう法律関係の資格を取るのはあきらめたほうが良いと思うのが普通かもしれませんが、実はその救済措置に引っかからないことを前提とした制度設計が求められるほど法律関係の資格試験が難しくなりすぎているというのが実情ではないでしょうか。
年代別・男女別の合格率
行政書士試験は合格者の属性が比較的細かく公開されています。公式ページに行けば各年代の男女ごとの受験者数と合格者数が分かります。各年代の合格率を男女別に計算してみると次のようになりました(小数第3位以下切り捨て)。
| 10歳代(男性) | 10歳代(女性) | |
| 平成29年度 | 10.49% | 6.97% |
| 平成28年度 | 12.56% | 2.33% |
| 平成27年度 | 11.44% | 3.44% |
| 20歳代(男性) | 20歳代(女性) | |
| 平成29年度 | 20.95% | 13.08% |
| 平成28年度 | 11.34% | 7.75% |
| 平成27年度 | 17.68% | 12.46% |
| 30歳代(男性) | 30歳代(女性) | |
| 平成29年度 | 20.21% | 16.13% |
| 平成28年度 | 11.78% | 9.92% |
| 平成27年度 | 16.21% | 15.42% |
| 40歳代(男性) | 40歳代(女性) | |
| 平成29年度 | 16.65% | 12.30% |
| 平成28年度 | 10.56% | 9.13% |
| 平成27年度 | 13.21% | 10.26% |
| 50歳代(男性) | 50歳代(女性) | |
| 平成29年度 | 12.97% | 10.74% |
| 平成28年度 | 9.17% | 6.65% |
| 平成27年度 | 9.72% | 10.16% |
| 60歳代以上(男性) | 60歳代以上(女性) | |
| 平成29年度 | 11.20% | 6.06% |
| 平成28年度 | 8.25% | 6.06% |
| 平成27年度 | 7.07% | 4.18% |
| 全年代(男性) | 全年代(女性) | |
| 平成29年度 | 16.74% | 12.93% |
| 平成28年度 | 10.49% | 8.42% |
| 平成27年度 | 13.51% | 11.99% |
行政書士試験は男性のほうが合格率が高いです。平成27年(2015年)度~平成29年(2017年)度の3年間で女性のほうが合格率が高いのは平成27年(2015年)度の50歳代のみです。特に10歳代、20歳代の若い女性の合格率が低くなっていると思います。
ちなみに宅建試験は女性のほうが合格率が高いです。
| 男性 | 女性 | |
| 平成29年度(2017年度) | 15.1% | 16.8% |
| 平成28年度(2016年度) | 14.7% | 17.0% |
宅建試験、社労士試験は合格者に占める女性の割合が比較的高いことも特徴です。平成29年度は宅建試験合格者の33.59%、社労士試験合格者の36.2%が女性でしたが、行政書士試験の女性合格者の割合は22.05%とやや低く、土地家屋調査士試験にいたっては例年合格者の約95%が男性です。
女性が多く受けている試験はそうでない試験と比べると競争率が高いと思います。大学入試でも大学進学率25%強(男子40%、女子12%)の頃は成績1~10にまんべんなく男女が入っており、かつ成績上位者が大学に進学していたと仮定すれば、成績の良い「成績8下位~7の中位くらいまでの女子」を差し置いて、彼女らよりも成績の良くない「成績7下位~6の中位くらいまでの男子」が大学に進学していたはずですが、時代が進み、その層の女子が大学に進学するようになれば、同様の層の男子の約半分は女子に入れ替わり、その約半分の男子と、それよりも下の層の男子は下にはじき出されてしまいます(最初にその事態に直面したのが第二次ベビーブーム世代の男性たちだと思います)。特に女子がよく受けている文系学部と医療系学部はその影響が大きいと思います。大まかに言って男女が半々くらいいて、男子は文系学部も理系学部も受けるのに、昔よりも大学進学率が大幅に増えている女子は文系学部と医療系学部に偏在しているというのでは文系学部と医療系学部が競争過多になってしまいます。諸説ありますが、ネットで検索すると出てくるサイトの1つによると、大学生の文理割合はおおむね7対3で男子は5.5対4.5、女子は8対2で文理に分かれるそうです。
そう考えると、土地家屋調査士試験は合格者が男性ばかりの今が狙い目の試験です。合格者の約半数が女性になる前に早く受けたほうが良いです。早く受けないといつか女性がたくさん入ってきて、今、試験に合格している層の男子の約半分は試験に合格できなくなりますよ。もし試験を受けるなら高級品で実績も抜群の東京法経学院の講座を利用して短期合格するのがおすすめです。
ところで土地家屋調査士試験の合格者の約5割を輩出している資格予備校やフルカラーテキストの調査士講座のことをご存じでしょうか? 当サイトおすすめの土地家屋調査士試験、測量士補試験の予備校講座はこちらです。リンク先で詳細をご確認下さい。
通信講座・通学講座・書籍・メディア教材で
資格取得をお手伝いします。
有力資格試験の合格指導専門校 東京法経学院
難関資格試験の通信講座ならアガルートアカデミー
フルカラーテキストの調査士講座
フルカラーテキストの測量士補講座