当サイトはアフィリエイトプログラムを利用して商品の紹介を行っています。
再測する観測区間を求める問題
試験問題 2014年度 No.12
図12は、水準点Aから固定点(1)、(2)及び(3)を経由する水準点Bまでの路線を示したものである。 この路線で公共測量における水準測量を行い、表12に示す観測結果を得た。 再測する観測区間はどれか。次の中から選べ。
ただし、往復観測値の較差の許容範囲は、Sを観測距離(片道、km単位)としたとき、
2.5mm√Sとする。なお、関数の数値が必要な場合は、巻末の関数表を使用すること。
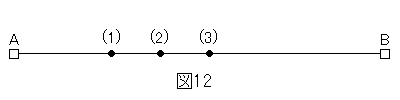
| 観測区間 | 観測距離 | 往路の観測高低差 | 復路の観測高低差 |
|---|---|---|---|
| A~(1) | 500m | -8.6387m | +8.6401m |
| (1)~(2) | 250m | -20.9434m | +20.9448m |
| (2)~(3) | 250m | -18.7857m | +18.7848m |
| (3)~B | 1,000m | +0.2542m | -0.2526m |
- A~(1)
- (1)~(2)
- (2)~(3)
- (3)~B
- 再測の必要はない
解き方
- それぞれの観測区間の「往路の観測高低差と復路の観測高低差の差」を求める。
- それぞれの観測区間の「許容範囲」を求める。
- 上記2つを比べて再測する区間を見つける。
往路の観測高低差と復路の観測高低差の差
- A~(1)は、|-8.6387m+8.6401m|=0.0014m=1.4mm
- (1)~(2)は、|-20.9434m+20.9448m|=0.0014m=1.4mm
- (2)~(3)は、|-18.7857m+18.7848m|=0.0009m=0.9mm
- (3)~Bは、|+0.2542m-0.2526m|=0.0016m=1.6mm
許容範囲
許容範囲は2.5mm√Sで求めます。Sの単位はkmです。たとえば観測区間A~(1)は500mなので、これを0.5に直して計算します。
- A~(1)は、2.5mm√0.5=1.76(以下省略)mm
- (1)~(2)は、2.5mm√0.25=1.25mm
- (2)~(3)は、2.5mm√0.25=1.25mm
- (3)~Bは、2.5mm√1=2.5mm
計算方法が分からない人は関数表に載っていない数字のルートの取り方の少数点が付いているとき1・2を参照のこと。
答え
許容範囲を超える差が出ているのは(1)~(2)の観測区間です。
おまけ
もし、個々の観測区間がすべて許容範囲を満たしていても、すぐに「再測の必要はない」を選んではいけません。観測区間全体で見ると許容範囲を満たしていないことがあるからです。
上で解説した問題を例にとると、「往路の観測高低差」を全部足すと-48.1136m、同じく「復路の観測高低差」を全部足すと48.1171mなので、観測区間全体(A~B)の「往路の観測高低差と復路の観測高低差の差」は、|-48.1136+48.1171|=0.0035m=0.35cm=3.5mmとなります。
全区間は2000m(=2km)なので、許容範囲は2.5mm√2=3.535525mm。
許容範囲3.535525mmに対して誤差は3.5mm。この問題は観測区間全体で見ると許容範囲を満たしています。
仮に許容範囲が3.335525mmだったりして誤差が許容範囲を超えているときは、個々の観測区間を調べたら、どこかに再測すべき区間が見つかるはずなのですが、問題によっては観測区間全体で調べると許容範囲を超えているのに、個々の区間はすべて許容範囲を満たしている場合があります。そういうときは観測距離が最も長い区間(上の問題だと(3)~B)を再測することになるそうです。どこで見たのか忘れてしまいましたが、そんな問題をどこかで見たような気がします。
個々の観測区間に加えて、観測区間全体で調べてみても許容範囲を満たしているときは、もちろん再測の必要はありません。
ところで土地家屋調査士試験の合格者の約5割を輩出している資格予備校やフルカラーテキストの調査士講座のことをご存じでしょうか? 当サイトおすすめの土地家屋調査士試験、測量士補試験の予備校講座はこちらです。リンク先で詳細をご確認下さい。
通信講座・通学講座・書籍・メディア教材で
資格取得をお手伝いします。
有力資格試験の合格指導専門校 東京法経学院
難関資格試験の通信講座ならアガルートアカデミー
フルカラーテキストの調査士講座
フルカラーテキストの測量士補講座