当サイトはアフィリエイトプログラムを利用して商品の紹介を行っています。
平均河床高の標高を求める問題
試験問題 2014年度 No.28
表28は、ある河川の横断測量を行った結果の一部である。図28は横断面図で、この横断面における左岸及び右岸の距離標の標高は20.7 m である。また、各側点間の勾配(こうばい)は一定である。この横断面の河床部(かしょうぶ)における平均河床高の標高を m 単位で少数第1位まで求めたい。最も近いものを次の中から選べ。なお、河床部とは、左岸堤防表法尻(のりじり)から右岸堤防表法尻までの区間とする。
| 側点 | 距離( m ) | 左岸距離からの比高( m ) | 側点の説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 左岸距離標上面の高さ |
| 0.0 | -0.2 | 左岸距離標地盤の高さ | |
| 2 | 1.0 | -0.2 | 左岸堤防表法肩(のりかた) |
| 3 | 3.0 | -4.7 | 左岸堤防表法尻 |
| 4 | 6.0 | -6.2 | 水面 |
| 5 | 8.0 | -6.7 | |
| 6 | 10.0 | -6.2 | 水面 |
| 7 | 13.0 | -4.7 | 右岸堤防表法尻 |
| 8 | 15.0 | -0.2 | 右岸堤防表法肩 |
| 9 | 16.0 | -0.2 | 右岸距離標地盤の高さ |
| 16.0 | 0.0 | 右岸距離標上面の高さ |
図28 河川横断面図

- 14.3m
- 14.5m
- 14.9m
- 15.4m
- 15.8m
図に数字を入れる
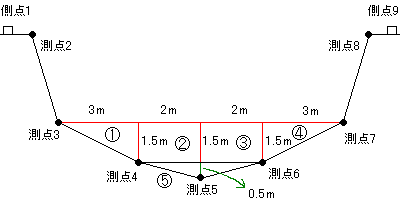
河床部の面積を求める
河床部とは左岸堤防表法尻(測点3)から右岸堤防表法尻(測点7)までの区間のことです。問題文にそう書いてあります。
三角形①は、3×1.5÷2=2.25㎡
四角形②は、2×1.5=3.0㎡
四角形③は、2×1.5=3.0㎡
三角形④は、3×1.5÷2=2.25㎡
三角形⑤は、4×0.5÷2=1.0㎡
以上の①~⑤を合計すると、2.25㎡+3.0㎡+3.0㎡+2.25㎡+1.0㎡=11.5㎡
平均河床高を求める
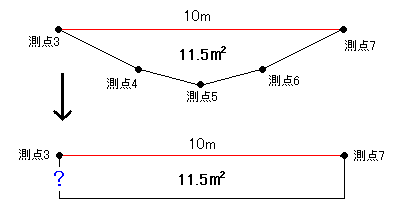
求めたいのは図の中の?のところです。平均河床高というのは、高さを均一にしたらどうなるかってことなので。
横10m×縦 ? m=11.5㎡
11.5㎡÷横10m=縦1.15m
というわけで平均河床高は1.15mです。
平均河床高の標高を求める
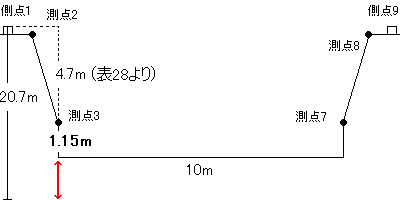
一番左の標高20.7mは問題文中に書いてあります。求めたいのは赤色のところの長さです。
20.7-(4.7+1.15)=14.85
というわけで平均河床高の標高は14.85mです。
これに最も近い3.の14.9mが正解です。
これと同じパターンの問題が2008年(平成20年)度にも出ていますが、 そのときは問題用紙に図が無かったので、表を参考にして自ら図を描いて考えないといけない問題でした。
ところで土地家屋調査士試験の合格者の約5割を輩出している資格予備校やフルカラーテキストの調査士講座のことをご存じでしょうか? 当サイトおすすめの土地家屋調査士試験、測量士補試験の予備校講座はこちらです。リンク先で詳細をご確認下さい。
通信講座・通学講座・書籍・メディア教材で
資格取得をお手伝いします。
有力資格試験の合格指導専門校 東京法経学院
難関資格試験の通信講座ならアガルートアカデミー
フルカラーテキストの調査士講座
フルカラーテキストの測量士補講座