PR・広告。
当サイトはアフィリエイトプログラムを利用して商品の紹介を行っています。
当サイトはアフィリエイトプログラムを利用して商品の紹介を行っています。
土地の面積を求める問題
試験問題 2014年度 No.27
図27は、境界点A、B、C、Dで囲まれた土地を表したものであり、直線ADは道路との境界線となっている。この道路が拡幅(かくふく)されることになり、新たな道路境界線PQが引かれることとなった。直線ADと直線PQが平行であり、拡幅の幅(はば)が3.0 m である場合、点P、B、C、Qで囲まれた土地の面積は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。
なお、点A、B、C、Dの平面直角座標系における座標値は、表27のとおりとする。関数の数値が必要な場合は、巻末の関数表を使用すること。
| 点名 | X座標(m) | Y座標(m) |
|---|---|---|
| A | -15.000 | -33.000 |
| B | +17.000 | -33.000 |
| C | 0.000 | +30.000 |
| D | -15.000 | +15.000 |
図27
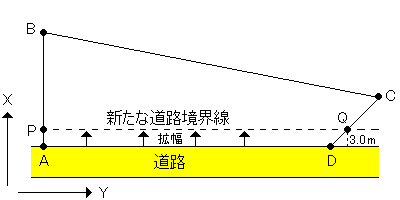
- 1,115.50㎡
- 1,219.50㎡
- 1,368.00㎡
- 1,462.00㎡
- 1,507.50㎡
解き方
- 図に線を引く。四角形や三角形を作る。問題によっては台形を作ることもある。ちなみに台形の面積を求める公式は、(上底+下底)×高さ÷2です。
- 表27の数字を使って各辺の長さを算出し、それを図27に書き込む。
- 面積を求める。
図に線を引いて数字を入れる
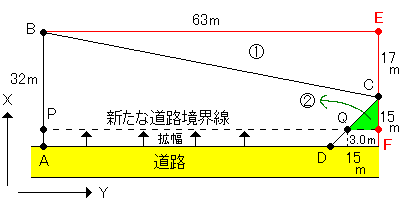
面積を求める
四角形BEFPから三角形①と三角形②を引くと答えが出る。
四角形BEFPは、(32m-3m)×63m=1827㎡
三角形①は、63m×17m÷2=535.5㎡
三角形②は、(15m-3m)×(15m-3m)÷2=72㎡
1827㎡-535.5㎡-72㎡=1219.5㎡
というわけで答えは2です。
もしかすると三角形②の辺QFの長さが分からない人がいるかもしれませんが、そういう人は15×15の正方形のことを考えてみてください。
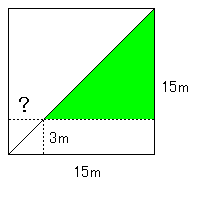
ところで土地家屋調査士試験の合格者の約5割を輩出している資格予備校やフルカラーテキストの調査士講座のことをご存じでしょうか? 当サイトおすすめの土地家屋調査士試験、測量士補試験の予備校講座はこちらです。リンク先で詳細をご確認下さい。
通信講座・通学講座・書籍・メディア教材で
資格取得をお手伝いします。
有力資格試験の合格指導専門校 東京法経学院
難関資格試験の通信講座ならアガルートアカデミー
フルカラーテキストの調査士講座
フルカラーテキストの測量士補講座